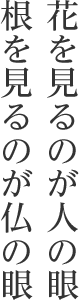人生の算数
2月を迎える時期、各地寺院で除災招福諸祈願の節分会が行われており、
先日、ある同宗派寺院の節分会に助法出仕させていただきました。
法要後、寺院の住職様が参詣者にされた法話が印象に残りました。
『人生における算数』
「足し算」
人生において加えられていくもの 身につくもの
「引き算」
人生において失っていくもの 減っていくもの
「掛け算」
人生において工夫して増していくもの
「割り算」
人生において分けられるもの
住職様は、それぞれを人生経験などから具体的に示されました。
私も自身の経験に照らしながら法話を拝聴させていただき、
なるほど人生とはそういうものかもしれないと、改めて整理して考えました。
生きていく時間の経過には足し算と引き算が必ずある。
足されるもの、引かれるもの、それは目に見えるもの見えないもの双方を含め、
おそらくどなたにおいても、いくつも思い浮かぶものがあろうかと思います。
さて、人生の掛け算、割り算はどうか。
これは人の気持ちの持ちようで生まれるもの。
例えば、掛け算。
自分の発心によって良い行いを実践し、また周囲にも浸透していく工夫を施し、
その波及がやがて大きな成果につながった経験。
苦手とする相手を理解して受け入れ、知恵や力を合わせた結果、
新しい発見、成長飛躍につながった経験。
逆に、自分ひとりくらいと粗雑な気持ちでしてしまう悪い行い。
いつしか悪業の芽は広く人に伝わり、環境自体を劣悪化させてしまった経験。
弘法大師曰く、「物の興廃は人による。人の昇沈は道にあり。」
人生の掛け算のごとく、人の善意、悪意は広がり増していくものです。
そして割り算。
喜びや利益となることを独り占めすることなく、
与え、分け合って、徳を広げてみよう。
「与えることの価値」がここにあります。
反面、悲しみや苦労は、分かち合うことで個々の負担を軽減する。
割り算は共感。
お釈迦さまの説かれた「抜苦与楽」の精神ではないでしょうか。
人生の足し算、引き算には、カタチ有れば無形もある。
不変も有れば無常もある。
もともと不如意である一生涯。
それを日頃の心得や精進によって掛け算と割り算がなされることで、
より豊かなものにできないでしょうか。
小学校で習った算数。
人生に置き換えて、そこに悦びのヒントがある気がする。
合掌