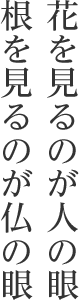葬送を考える
賑やかで期待に満ちていた令和時代の幕開け。
ここにきてそのムードも落ち着きつつあります。
早いもので今年も半年が過ぎました。
このたび、本宗各寺院が集い、葬送について学ぶ機会がもたれました。
枕経、通夜、葬儀について講師の御住職様よりお話をお聴きし、
さらに納棺の作法と意味を御住職様の実演によって学びました。
情報と意見交換を含め、通して「心得」を教わることが出来たように思います。
さて、昨今の葬送の在り方については、常々話題になり考える機会があります。
世の中の葬儀形式やニーズ、受け入れの間口が急速に変化しているからです。
これから先、もっと広い視野より情報を集めて学び、地域にも照らし考えを深め、
見極めていかなくてはならないと感じています。
ひと言でいうと葬儀には地域差があります。
寺院そのものの意義も地域により異なるのかもしれません。
地域や世代間の課題を考える点において寺院の責任は小さくはありません。
葬儀には、世間の意識や基準があり、葬儀社の立場があり、
寺の歴史的立場があり、多くの価値観が混在しております。
そして、現代は多様化に伴う「取捨選択」の時代であり、
葬儀の意義そのものがその対象となっており、
葬儀の在り方が縮小化されていることは否めません。
講師の御住職様が、誰のための葬送作法なのかということを強く仰っておりました。
一番は亡き人、次には遺族親族であることです。
深い悲しみにある遺族が支え合い、故人と遺族のご縁の方々にも支えられながら、
なんとか故人とのお別れをしなくてはなりません。
故人の御旅立ちを見送ったあとから迫る寂しさのなかに、
『これで良かったのだ』
と、『安心』を与えることができるのは僧侶の大切な務めです。
そのために、いまいちどその意義を遺族の心に灯すため、
「柔軟に伝えていく手法」の必要性を感じております。
葬儀に関わる方、それぞれのお立場をわきまえつつ実践していき、
ひとりでも多くの方に『安心』してもらえるように尽くさなくてはいけません。
このたびの講習会はその点において大変勉強になり、
あらためて考える機会をいただきました。
寺院、僧侶に対する厳しい意見は多く、それを真摯に受け止めつつ、
何が欠けているのかを見直していくことは必然的な作業であることのひとつ。
同時に、寺院、僧侶だからこそ出来きることや求められていることを知ることも
大いに必要であり前向きな作業となります。
合掌